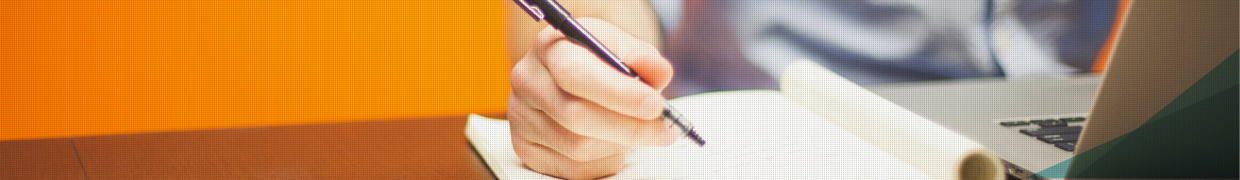
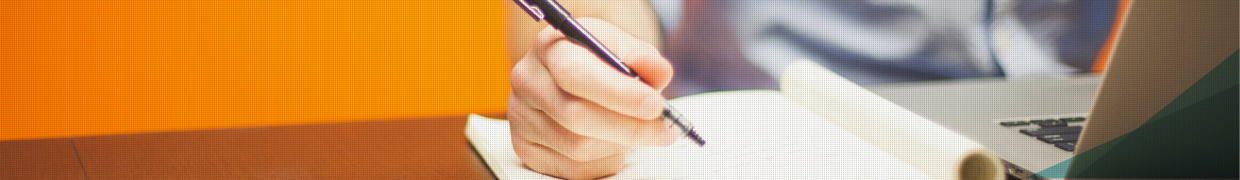

2017.10.19
通勤中又は業務中に交通事故被害に遭った場合、被害者は、その加害者から賠償金を受領することも勿論可能ですが、労災保険からの給付を受けることも可能です。
両方からの給付を受けることが可能だとしても、二重に損害の填補を受けることは妥当ではないので、両給付間において調整が行われます(調整方法については、非常に複雑な議論のあるところですが、ここでは割愛します。)。
ただし、労災保険からの給付は、損害発生と同時に支払われるわけではなく、その支払にはある程度の期間を要します。
そのため、労災保険からの給付を受けたとしても、現実に給付金を受け取るまでの期間に対応する遅延損害金(支払が遅れたことによる利息)は発生し、それを加害者に対して請求する余地が残るのではないか、ということが問題となります(被害者の被った損害に対しては、事故発生日から、年5%の遅延損害金が付加されます。)。
この点に関し、最高裁は、例外的な場合を除き、被害者が労災保険給付を受けた場合、当該給付が填補の対象としている損害は発生と同時に填補されたものと考える、と判断しています。すなわち、「制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り」、損害発生と同時に填補されたものと評価し、労災保険給付が現実に行われるまでの遅延損害金の請求は認めないと判断しています。
ところが、今般、この「特段の事情」を認めた裁判例が登場しました(東京高裁平成28年8月31日判決)。
この裁判例の事案は、標準的な処理期間から著しく遅滞して労災保険給付が行われたもので、最高裁のいう「特段の事情」に該当すると認められたものです。このような場合には、損害発生と同時にその填補が行われたと考えることはできず、別途、遅延損害金の請求を求めることも可能となります。
今後問題となるのは、「特段の事情」と評価すべき期間がどの程度なのか(どの程度の遅滞があれば特段の事情に当たるのか)という点だと思われます。
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。




交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.