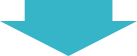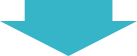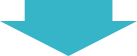私の解決事例のご紹介
賠償金額の増額だけではなく、
相談者一人ひとりが事故を乗り越え
再出発できるための解決実績。
自賠責後遺障害等級11級でも将来介護費用が認定された事例
Oさん
自賠責後遺障害等級は11級でも、入院等に伴う廃用の影響を考慮し、将来介護費用が認められた事例
事件内容
Oさんは、交通事故によって骨折し、長期間の入院を余儀なくされました。
骨折部分は癒合したのですが、ご高齢であったことから、長期間の入院等の影響で筋力低下が進み、介護を要する状態になってしまいました。
ご相談者様のお悩み
自賠責保険における後遺障害等級は11級であり、それだけを見ると、介護費用の認定は難しいようにも思われます。
弁護士が交渉しましたが、保険会社も十分な介護費用の支払には応じませんでした。
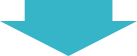
解決内容
後遺障害等級が高い場合(1ないし3級)であれば、介護費用を認めさせるのはそれほど難しい話ではないと思います。
しかし、11級となると、随分と話が違います。
裁判例を調べましたが、当時は、あまり参考になるような例も見当たりませんでした。
確かに後遺障害等級こそ低いですが、ご高齢の方であれば、入院に伴って急激に筋力が低下し、歩けなくなることも珍しくはないはずです。
そういった当たり前の因果関係すら認められないのはおかしい、弁護士として何とかしなければならないと考え、訴訟提起をしました。
解決までには時間がかかりましたが、裁判所も、ある程度の将来介護費用を認定してくれました。

この事案は、ご高齢の方が交通事故に遭って入院し、その間に廃用が進んでしまった場合に参考になるものです。
加齢とともに体の機能が徐々に衰えてしまうのはやむを得ないと思いますが、交通事故によってその進行が数年早くなったといえる場合は珍しくないはずです。
認めさせるのは簡単ではないと思われますが、後遺障害等級が低くても介護費用の認定を簡単にあきらめる必要はないことを示す良い例だと思います。

後遺障害非該当・相手方免責主張の状態から、訴訟を通じ多額の賠償金等の回収へ
Kさん
相手方が責任を争い(免責主張し)、後遺障害非該当の状態から、訴訟を通じ多額の賠償金等を回収した事例
事件内容
信号のある交差点における自動車同士の出会い頭事故によって、Kさんが受傷しました。
信号の色を巡る主張が対立しており、相手方は免責を主張しました。
また、Kさんは、ご自身で後遺障害の申請をしていましたが、その結果は非該当でした。
ご相談者様のお悩み
相手方が責任を争っている状況を何とかしたいという点、そして、後遺障害非該当の結果を何とかしたいという点が最大の悩みでした。
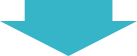
解決内容
まず、後遺障害等級に関しては、私が異議申立てを行いました。その結果、後遺障害等級を獲得することができました。
後遺障害等級に関しては、その後、訴訟においても再び争点になりました。しかし、結局、裁判所は、自賠責の判断を維持する結論に達しています。
自賠責で後遺障害等級が認定された場合には、それを争う側が相当説得的な主張立証をしない限り、自賠責の判断が維持される傾向が強いのです。
逆に、自賠責で後遺障害非該当と判断されたままだと、こちらが相当説得的な主張立証をしない限り、裁判所も後遺障害等級に該当するとの判断には至りません。
本件では、こちら側も医学的な観点から自賠責の判断が妥当であることを主張立証し、自賠責の判断が覆るのを阻止したというわけです。
次に、信号の色についてはなかなか決め手に欠ける悩ましい問題でした。
最終的には、相手方がある程度の責任を認める内容で解決に至っています。過失相殺された分については、Kさん加入の自動車保険からの人身傷害保険金で填補されました。
以上のような手続を経て、多額の賠償金等の回収を実現することができました。

この件は、かなり難しい案件でした。
当初の状態ですと回収額は極めて少額に止まった可能性が高いのですが、後遺障害等級にしても、信号の問題にしても、全てが上手く進み、最終的には多額の回収に繋がりました。
解決までには3年以上かかりましたが、私としても、「本当に上手くいった」と思える解決に至り、嬉しく思っています。

賠償金額の増額だけではなく、相談者一人ひとりが 事故を乗り越え再出発できるための解決実績。
後遺障害非該当であるものの、示談において後遺傷害部分の補償が認められる事例
Qさん等
後遺障害非該当でも、後遺障害に対する補償が示談の中で考慮される事例
事件内容
これは、いくつかの解決事例を踏まえたものです。
後遺障害が残ったことから、後遺障害の申請を行ったものの、自賠責保険において後遺障害等級が「非該当」と判断される場合があります。
そのような場合に後遺傷害部分の補償が受けられるのか否かは、実務的には悩ましい問題です。
ご相談者様のお悩み
自賠責保険における後遺障害として等級が認定されるためには、一定の基準を満たす必要があります。
その基準に至らない場合には、非該当となってしまうわけですが、非該当=完治(症状消失)ではないため、問題になってきます。
通常、示談交渉を担当する任意保険会社は、非該当の場合には、後遺傷害部分の補償を否認します。
しかし、症状が消失している(完治している)わけではないため、被害者としては、それでは納得できない心情になってしまいます。
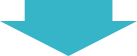
解決内容
このような場合には、訴訟での解決を目指す方法があります。訴訟であれば、実際に残っている後遺障害の内容に応じ、裁判所が後遺障害に対する補償の要否を判断します。そのため、非該当の場合でも残った後遺障害の程度に応じた補償が受けられる可能性は、示談の場合に比べると、高くなります(ただし、痛みや痺れといった目に見えない神経症状の場合には、そう簡単なことではありません)。
難しいのは、示談交渉での解決を目指す場合です。
私の経験上、体の傷痕が残っているものの、認定基準上の大きさには至らない場合には、傷痕の形状等を考慮して一定程度後遺障害慰謝料が認定される例は、示談交渉でも珍しくないと思います。
問題は、むちうち等に伴う痛みや痺れといった神経症状の場合です。これらは目に見えない後遺障害であるため、自賠責保険で非該当と認定された場合、通常、保険会社は後遺障害部分の補償には応じません。
しかし、私の経験上、中には幾分かの支払に応じてくる例も存在します。応じる理由は様々だと思いますが、タイミングの問題が大きいように感じています。つまり、保険会社として、当該事案を早期に解決させたいと思っているか否か、という点に左右される傾向があるように思います。

このように、「非該当」の場合には、後遺障害に対する補償を受けることは、簡単ではなくなります。
そのため、異議申立て等の不服申立て手続を経て、後遺障害等級を獲得することが、まずは重要になってきます。
しかし、認定基準に照らし、自賠責保険では非該当とならざるを得ない例もあります。その場合には、後遺障害の内容を考慮しながら、方針を考えていくことになります。

交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。