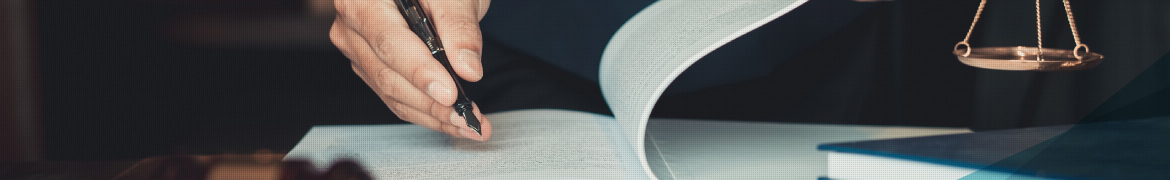
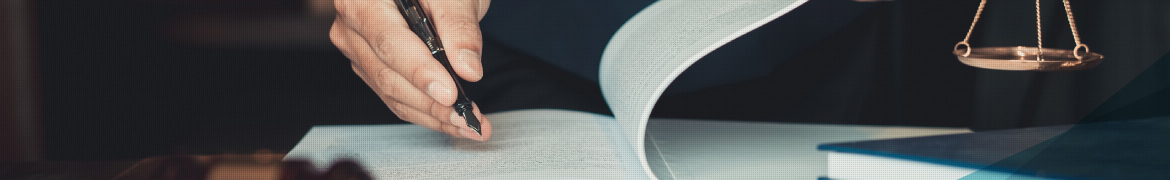

2021.05.07
目次
交通事故で人身傷害が発生した場合には、主に、①加害者の加入する自動車保険の対人賠償責任条項で補償を受ける方法と、②被害者自身が加入している自動車保険の人身傷害補償条項で補償を受ける方法が存在する。一般的に、被害者側にも結構な過失が存在する場合、加害者側の保険会社は対人賠償責任条項での支払を拒否してくることがあり、その時には、被害者自身が加入している人身傷害補償条項で補償を受けることを先行させていくことになる。
そして、人身傷害補償条項に基づく保険金(人身傷害保険金)は、被害者の過失の程度にかかわらず、約款で定められた支払基準に従って算定される。ポイントは「過失の程度にかかわらず」という部分である。加害者との関係では、請求可能な損害額には過失相殺が行われるので、被害者の過失に相当する割合だけ賠償額は減じられる。しかし、そのように減じられた部分も、被害者の損害自体は発生している。人身傷害保険金は、そのように加害者側からは填補されない損害部分(=過失相殺された部分)に優先的に充当されることになる。
例えば、ある交通事故によって、被害者Aには、治療費・休業損害・慰謝料等として、「100万」の損害が生じたとする。ただし、Aに3割の過失があれば、加害者Bに請求できる損害額は、「70万」となる。そうすると、過失相殺された「30万」の部分は、加害者Bからは補償されないこととなるが、人身傷害保険金はそれを補填する効果を持っている。
したがって、人身傷害保険金として、先に、「40万」が支払われた場合には、その内の「30万」部分は、過失相殺されてしまう部分の損害を填補する効果を生じる。その結果、被害者Aの損害は、残り「60万」(100万-40万)となり、この金額であれば、加害者Bが支払うべき金額(70万)の範囲内に収まるから、結果的に加害者Bからは残りの損害額60万全額が支払われ、被害者Aとしては、合計で「100万」の補償を受けることが可能となる。
これが、従来までの人身傷害保険の一般的理解である。しかし、福岡高裁判決は、そのような方向性を変えるものである。
対人賠償責任保険の支払を拒否され、人身傷害保険金の支払を先行させる場合、その人身傷害保険金の中には、2種類の性質を持った部分が存在することになる。すなわち、①強制保険である自賠責保険から支払われるべき部分と、②その上澄みとして任意保険会社が負担すべき部分である。重大な怪我を伴わない事案であれば、自賠責保険の支払基準に従って保険金の額を計算していくと、自賠責保険の保険金額(傷害部分120万円)を下回る場合も多いところ、そのような事案であれば、人身傷害保険金として支払われるのは、①の部分(自賠責保険から支払われるべき部分)のみとなり、②の上澄み部分は生じてこない。
この福岡高裁の判決は、先行して支払われた人身傷害保険金の内、①の要素を持つ部分(自賠責部分)については、被害者の過失部分を填補する機能を有していないという判断を示したものである。もう少し正確に述べると、人身傷害保険金の支払に伴い、被害者の有していた自賠責保険金請求権が合意によって保険会社(人身傷害保険保険会社=人傷社)に移転し、移転した権利に基づいて人傷社が自賠責保険金を回収していることから、その部分については、加害者が被害者に賠償金を支払ったことと同視し得るという判断である。
その結果、先の事例で説明すると、被害者Aが人身傷害保険金として40万を受領した場合、人傷社は40万を自賠責保険に請求して回収を行うことから、被害者Aとしては加害者Bから40万の賠償金を受領したことと同視され、したがって、その後に被害者Aは、加害者Bからは30万(70万-既払い40万)しか受領できない。この場合の被害者Aの総取得額は、人身傷害保険を合わせても100万ではなく、70万に留まってしまう。これでは、結果的に、人身傷害保険に加入していた意味(過失部分の填補)が殆ど無いことになってしまう。
本来、保険法や人身傷害保険の約款に基づけば、人身傷害保険の支払に伴って保険会社が自賠責保険金の請求権をすべて取得すると考えることは、当然には認められない。被害者に過失がある場合には、人身傷害保険金はその過失部分を補填し、補填した上で余剰部分があれば、余剰部分に限って請求権を代位取得するに過ぎない。
しかし、人身傷害保険の支払に際して作成されている協定書には、定型的な文言として、自賠責保険金の請求権が移転する旨の文言が入っている。福岡高裁判決は、そのような「債権譲渡の合意」(判決文では「受領権限の委任」と表現)の存在を認定することで、保険法や約款に基づいて本来的に生じてくる代位の範囲を超える権利移転を認めている。
この点に関しては、そもそも保険契約に関して、約款の範囲を超える権利譲渡(しかも被保険者に不利な権利譲渡)の合意を簡単に認めることには違和感を覚える。個別の権利譲渡合意と請求権代位は理論的には別物であるが、代位に関しては、保険法25条が差額説の立場を採用し、さらに最高裁が訴訟基準差額説に立つことを明言しているところ、同条は強行規定であり同条よりも不利な特約は無効とされていることから(保険法26条)、安易に事後的な個別合意による権利譲渡を認定すると、強行規定とした法の趣旨が没却されるのではないだろうか。
確かに実際の実務においては、人傷社による自賠責保険金回収は当然に行われていることであるし、そのような回収を行うことは、多くの弁護士であれば、当然に想定していることであり、その点に誤解はないかもしれない(加害者との間で訴訟にならず、示談で解決する場合には、人傷社による自賠責保険回収分が後に不当利得として返金されることもないはずである)。問題は、加害者との間で訴訟になった場合である。その場合、人傷社による自賠責保険金の回収が行われていたとしても、それが当然に加害者による支払と同視されることまでは、通常の弁護士であれば、想定していなかったはずである。これまでは、そのような理解を前提に、裁判所の判決や和解に基づいて、人傷社が回収し過ぎた自賠責保険金を加害者側に返還する処理が行われてきた。多くの弁護士としても、そのような処理が行われることを前提に、人傷社による自賠責保険金の回収を黙認してきたように思う。また、加害者側の弁護士としても、人傷社による自賠責保険回収部分は裁判の結果によっては返金処理がされ得る暫定的なものとして、それを当然に加害者による既払い金として控除すべきであるとも主張しないことが一般的であった。しかし、この福岡高裁判決によると、訴訟の場面においても、人傷社による自賠責保険回収が直ちに加害者による支払と同視されてしまうため、被害者の過失相殺部分が填補されないという結果が生じてしまい、被害者側の通常の期待を裏切る結果となる。したがって、この点は、判決で指摘されているように、事後的に、被保険者と人傷社との間の問題として適切な調整が行われるべきである。要するに、回収し過ぎた自賠責保険金を人傷社が「被保険者(被害者)」に返金する処理が行われるべきである。元々は、訴訟の結果を前提とすれば過剰となる回収部分について、人傷社が加害者側に返金していたものを、被保険者(被害者)に返金するだけだから、人傷社としても実質的に大きな変更ではない。また、そのような返金の理論的な根拠としては、色々と考えられる。例えば、①被保険者からの人傷社への自賠責保険金請求権の譲渡合意は、後で加害者側との裁判の結果が出て、訴訟基準差額説に照らせば過剰な回収であったことが判明すれば、その点については加害者側又は被保険者に返金することを含意した合意であると解することが可能と思われる(返金合意を含んだ債権譲渡)。そのような合意であれば、保険法25条・26条との関係でも、強行規定とした法の趣旨が没却されるという事態にも至らないはずである。基本的にはそのような解釈が正当であると思われるが、②人傷社が、仮にそのような条件付きの返金合意を含んでいないと主張し、かかる主張が認められるのであれば、協定書取交し時において、約款を超える権利譲渡を含む協定書であったことの十分な説明が必要であったと考えられるから、そのような説明を怠って被保険者の合理的期待を裏切った点につき、説明義務違反を根拠とする損害賠償請求といった構成も考えられる。
ただ、返金額の算定には、少し悩ましい問題があるようにも思われる。すなわち、後遺障害がなく、傷害部分の自賠責保険金額の範囲内で収まるような案件において、先行して人身傷害保険金の支払を受ける場合には、①人身傷害保険金の支払基準に基づいて算定された金額と、②自賠責保険の支払基準に基づいて算定された金額とを比較すると、前者(人身傷害保険の支払基準)の方が低くなる。この場合、人身傷害保険の約款上、自賠責保険の支払基準額まで保険金の額を引き上げ、自賠責保険の支払基準に基づいた保険金を人身傷害保険金として支払うことになる。このような引上げ部分(②-①の差額部分)は、自賠責保険への請求権を人傷社が取得する前提で引き上げている部分といえるから、その部分に関しては、自賠責保険金請求権は合意に基づいて有効に移転し、上記のような返金は想定されていない部分であると考える余地があるのではないか。人身傷害保険金の支払基準に基づいて算定された額(①)に相当する部分は、被害者の過失部分を補填する機能を有していると考えるべきであるが、それを超える部分(自賠責保険金の支払基準への引上げ部分)については、そのような機能を当然に有しているとまでは言いにくい。被害者側としては、このような引上げ部分も含めて自らの過失部分を補填する機能を有していると期待している可能性はあるし、これまでの実務ではそのような期待が一般的であったように思われるが、それが「合理的な」期待であったといえるかは、微妙である。この引上げ部分は、人傷社として自賠責保険金を回収し得ることを前提として、人身傷害保険の支払基準に上乗せをしている部分であることから、この部分に関しては、上記のような返金合意が含意されていると解することは、少し違和感を覚える。また、その部分が返金されなかったとしても、被保険者の「合理的な」期待を裏切ったという根拠に基づく損害賠償請求の構成も難しいように感じる。返金額に関するこのような結論は、被害者の過失部分の補填機能との関係でみれば、訴訟を通じて加害者からの損害賠償金の支払いを受けた後に人身傷害保険金の支払を受ける場合と同じ結果ともたらすものであるから、妥当だと思われる。ただし、自賠責基準への引上げが行われた部分も含め、あくまで人身傷害保険金として支払われている以上は、保険法25条・26条が適用され、その趣旨を貫徹するという観点から、引上げ部分も含め返金の対象とする余地もあるように思われる。この点は、悩ましい問題である。
例を用いて説明すると、被害者Aの全損害が「100万」、被害者の過失を5割、人身傷害保険金として「40万」の支払を受ける場合を想定する。この場合には、自賠責保険の保険金額の範囲内で収まる場合であるから、人身傷害保険の支払基準で計算すれば、例えば「30万」にしかならないと仮定する。ここでは、自賠責保険の支払基準への引上げが10万行われることになる。そして、まず被害者Aが人傷社から40万の人身傷害保険金の支払を受け、その後に人傷社が自賠責保険から40万の回収を行えば、被害者Aが加害者Bから受領できる賠償金は、残り10万となる(100万の全損害から5割の過失相殺を行うと50万となり、そこから既払い40万を控除する)。もちろん、この場合の加害者Bへの請求は、訴訟で行う必要がある点には注意が必要である。そうすると、加害者Bへの訴訟が終結した時点で、被害者Aは、人身傷害保険金40万と、加害者からの賠償金10万の合計50万を取得していることとなる。そして、被害者Aには5割の過失があるから、過失相殺されている額は50万であるのに対し、人傷社からの支払保険金は40万に過ぎない。約款に従えば、本来は、代位は生じない事案である。ただし、自賠責保険の支払基準への引上げ部分の10万は有効に債権譲渡を受けていると解すべきであるから、その部分の自賠責保険金の回収は正当化され、返金の必要はない(とすべきように思うが、この点は異論があるところだと思う。)。これに対し、残りの30万部分(人身傷害保険金の支払基準に基づいて人傷社が本来的に負担すべき額)は、返金が行われるべきである。その結果、訴訟終結時点での回収額50万に、返金額30万が加算され、最終的には80万が被害者Aの手元に入ることとなる。
福岡高裁判決は、これまでの人身傷害保険を巡る実務上の一般的な運用とは異なるものであるため、一見すると、大きなインパクトがありそうにも思える。
しかし、加害者側が、人傷社による自賠責回収部分の既払い金控除を主張しない限り、この問題が顕在化することはないと思われる。従来から、判決になった場合には、判決結果に応じ、保険会社間では、人傷社が回収し過ぎた自賠責保険金を不当利得として加害者側に返還するといった処理が行われてきた。すなわち、人傷社に対する自賠責保険金の支払は、訴訟の結果によっては返金も必要となる暫定的なものであるから、加害者側としても、そのような暫定的な自賠責保険金の支払が当然に既払金に該当すると主張しない例が多かったと思われる。加害者側から見た場合、確かに福岡高裁判決が指摘するような利益も皆無ではないだろうが、とはいっても、わざわざこのような主張をする実益は決して大きなものではない。保険会社は、時には加害者側の立場で対応し、時には人傷社の立場で対応するのだから、実益が乏しいのであれば、手続はシンプルな方がよいはずである。したがって、なるべく、従来のままの方向性(既払金として控除するのではなく、訴訟の結果を踏まえ、保険会社間で返金調整を行う手法)で行きたいと思うのではないだろうか。
そのため、加害者側がこのような主張をすることが急に増える可能性は、高くはないように思われる。とはいえ、そのような主張をされる事案もあるだろうし、その場合には、人傷社との事後的な返金処理がスムーズに進むのかも現時点では不透明であるため、弁護士としては気持ちの悪さが残る。
人傷社との間で取り交わす協定書に「約款の定める範囲に限って譲渡する」という旨を明記しておけば、約款を超える回収部分は後で返金する旨の合意が含まれているという認定に流れやすいのかもしれない。ただ、私見としては、それがなくても返金合意は認定されるべきだと思う。
いずれにしても、前述したような回収し過ぎた部分を被保険者に返金する実務的な運用方法を早く確立してもらいたい。
この問題は、現時点ではまだ十分に論じられていない。
そのため、上記の見解も、私の個人的な意見に過ぎないので、その点はくれぐれもご注意ください。
この福岡高裁判決に対しては、上告受理申立がされているようなので、その結果をみるのが楽しみである。
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。




交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.