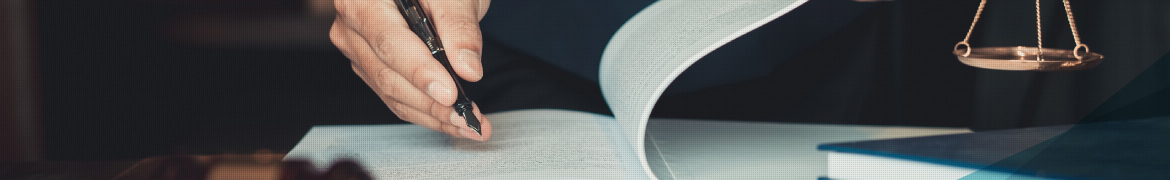
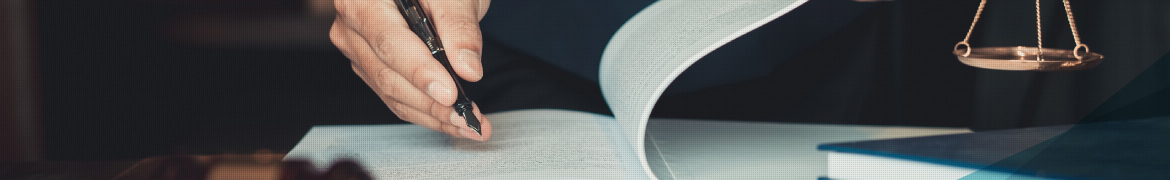

2020.04.25
目次
交通事故で、加害者が任意保険に加入している場合、治療費は、通常、保険会社から病院に対して直接支払われます。その結果、被害者は、窓口で治療費を支払う必要がありません。
事故から時間が経過すると、このような支払が打ち切られる場合があります。
加害者側の保険会社は、「症状固定日」までの治療費を支払う義務を負っています。症状固定日とは、「これ以上治療を続けても改善しない状態」を意味します。要するに、保険会社としては、その時点で症状固定段階に至っているとの考えに基づいて、治療費の支払を打ち切るわけです。その根拠としては、あまり根拠のない場合もあれば、主治医の見解を踏まえた場合もありますし、保険会社顧問医の見解による場合もあります。
これに対し、被害者又は主治医としては、「まだ症状固定に至ってはいないから、治療を継続すべきである」と考えている場合には、症状固定日を巡り、保険会社側の見解との相違が生じます。このような見解の相違から、被害者の意図に反した治療中の「打ち切り」という問題が生じるわけです。
そのような治療中の「打ち切り」が生じた場合、被害者としては、どのように対処すればよいのでしょうか?
以下では、主な選択肢について説明します。
交通事故が、通勤災害又は業務災害に該当する場合には、労災保険を使用し、そこから治療費を払ってもらう方法があります(療養補償給付又は療養給付といいます。)。
保険会社から「既に症状固定に至っている」と主張されている状態なので、労災保険から治療費を支給してもらえるのかは問題となり得るのですが、主治医が「症状固定には至っておらず、まだ治療が必要である」と判断している場合には、十分に可能性があります。したがって、この方法を用いる場合、主治医の考えを聞くことが重要だと思います。
労災保険が使用できる事案であって、主治医が治療の必要性を認めている場合には、労災保険の使用が非常に有効な選択肢となります。
交通事故が労災事故ではない場合には、ご自身の健康保険を使用した上で、自己負担部分をご自身で負担して治療を継続する方法があります。
「症状固定日」までの治療費については、加害者(実際には加害者加入の保険会社)から回収できる可能性がありますので、自己負担した部分は、後日、加害者に請求していくことになります。実際に回収できるか否かは、最終的に症状固定日がいつと判断されるかによります。場合によっては、症状固定日について、裁判所の判断を求める場合もあり得ます。裁判になった場合、症状固定日の判断については、主治医の意見が相当程度尊重される傾向があるように思います。
なお、この方法を用いる場合には、ご加入の健康保険組合に対し、第三者行為の傷病届を出すようにしましょう。
「被害者側」で加入している自動車保険(任意保険)に、人身傷害保険があり、それが使用できる場合には、人身傷害保険から打ち切り後の治療費を支払ってもらう方法も考えられます。
人身傷害保険とは、典型的には、自損事故などご本人の過失が大きい事故を起こして怪我をした場合に使用するもので、ご自身の自動車保険から治療費等を支払ってもらうことが可能です。この保険は、基本的にはご本人の過失の程度にかかわらず支払が可能な保険ですから、被害者となった交通事故にも使用できます(ただし、被害事故の場合には、通常、加害者側の任意保険が治療費を支払うため、人身傷害保険を使用する機会が乏しいのです。)。そこで、打ち切り後の治療費を人身傷害保険から払ってもらうという方法も、一応は存在します。
しかし、この方法は難航する場合が多いと思います。というのも、加害者側の保険会社が「症状固定」と判断している状況が一応存在しますので、(人身傷害保険を支払うのが別の保険会社であったとしても)支払を嫌がる場合が非常に多いのです。私の経験上も嫌がられたことが多いですが、応じてもらえたケースも中には存在します。したがって、有効とはいえないものの、一応は選択肢の一つといえます。
なお、人身傷害保険を使用する場合には、通常、健康保険の使用を求められますので、健康保険を使用した上で、自己負担部分を人身傷害保険の会社から支払ってもらう処理になります。
加害者は、任意保険だけではなく、自賠責保険にも加入しているはずです。
自賠責保険の傷害部分の保険金額は120万円ありますので、打ち切り後もその枠が残っている場合には、打ち切り後の治療費を自賠責保険に直接請求する方法が存在します。
ただし、自由診療を前提に相当期間通院を続けた後だと、殆ど枠も残っていない可能性も十分に考えられるところです(任意保険会社が治療費等の支払を行っていた場合、任意保険会社は自賠責保険会社に対して請求を行い、120万円の保険金額からの回収を行いますので、120万円の枠は減少していきます)。
方針の選択においては、主治医の意見が重要になってきますので、弊所でも、必要に応じて医師面談等を行った上で方針を検討する場合が珍しくありません。
もし主治医も「症状固定が妥当」と確信している場合には、依頼者様と協議し、症状固定の方針で進める場合もあります(ただし、症状等の内容によっては、後遺障害申請しても「非該当」になる可能性が高い場合には、安易に等級獲得を見込んで症状固定とするのは、リスクがある場合もあります。)。
ここでの対応を誤ってしまうと、後日、症状固定日の認定、後遺障害診断書作成の可否、健康保険の誤使用(労災保険を使うべき事案なのに)等の問題が生じる可能性もあります。
保険会社による打ち切り後も治療を継続し、後日症状固定にしたいと考えている場合には、弁護士に相談することが望ましいように思います。
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。




交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.